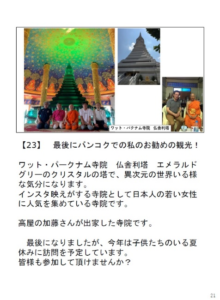【第2795例会】「国際奉仕活動について」本田会員(国際奉仕委員会)(2023年3月16日例会)
会長時間
『風の歌を聴け』 村上春樹
昭和54年「群像新人文学賞」に輝いた村上春樹のデビュー作であり、2年後には小林薫・真行寺君枝主演で映画化もされています。
物語の初めに、「この話は1970年の8月8日に始まり、18日後、つまり同じ年の8月26日に終わる」と書かれてある通り、東京の大学に通っている主人公が夏休みで芦屋の実家に帰省している18日間の夏の記録です。
主人公は50年前の大学生なのに車を与えられていて、バーで鼠という友人とビールばかり飲んで過ごしています。その友人と何人かの女の子と主人公のけだるい夏、特段何か起こるという話ではなく、淡々と記録が述べられる青春日記のようなものです。
それならば一体、この作品のどこに魅力があり、「群像新人文学賞」をとる事ができたのでしょうか。この作品には、物語が始まる前の第1章にこう書かれてあります。
「僕たちが認識しようと努めるものと、実際に認識するものの間には深い淵が横たわっている。どんな長いものさしをもってしても、その深さを測りきる事はできない。僕がここに書きしめす事ができるのは、ただのリストだ。小説でも文学でもなければ、芸術でもない。まん中に線が1本だけ引かれた1冊のただのノートだ」
この作品の新しい所は、心の痛み・葛藤を描く事はせず、むしろそんな事は言葉では書けないのだという前提に立って書かれている所です。(先月のサガンのように)心の痛み・葛藤、そういった心の内面・心理描写を丁寧に言葉に表現していく事が文学だと認識していたので、最初に読んだ時には軽く流して、あまり印象に残らなかったのでしょう。
しかし、改めて読んでみると、淡々と書かれた場面からも、決して癒されない苦しみや悲しみを感じとる事ができます。
たとえば、主人公は女の子と別れる時に「嫌な奴」というメモを残されます。また、昔の友達に連絡をとっても、「お前とは話したくない」と言われます。
それについて、主人公がどう思ったかという描写はありません。描写はありませんが、読者はそれを読んで、主人公がどう思ったかを感じとる事はできます。
この小説は、心の動きをあえて書かない事によって、書けないものを書こうとしている。そういう矛盾に挑戦している新しい文学だと思います。